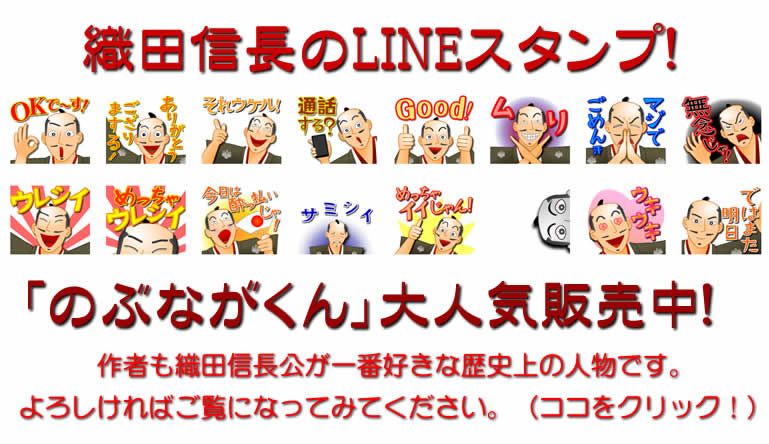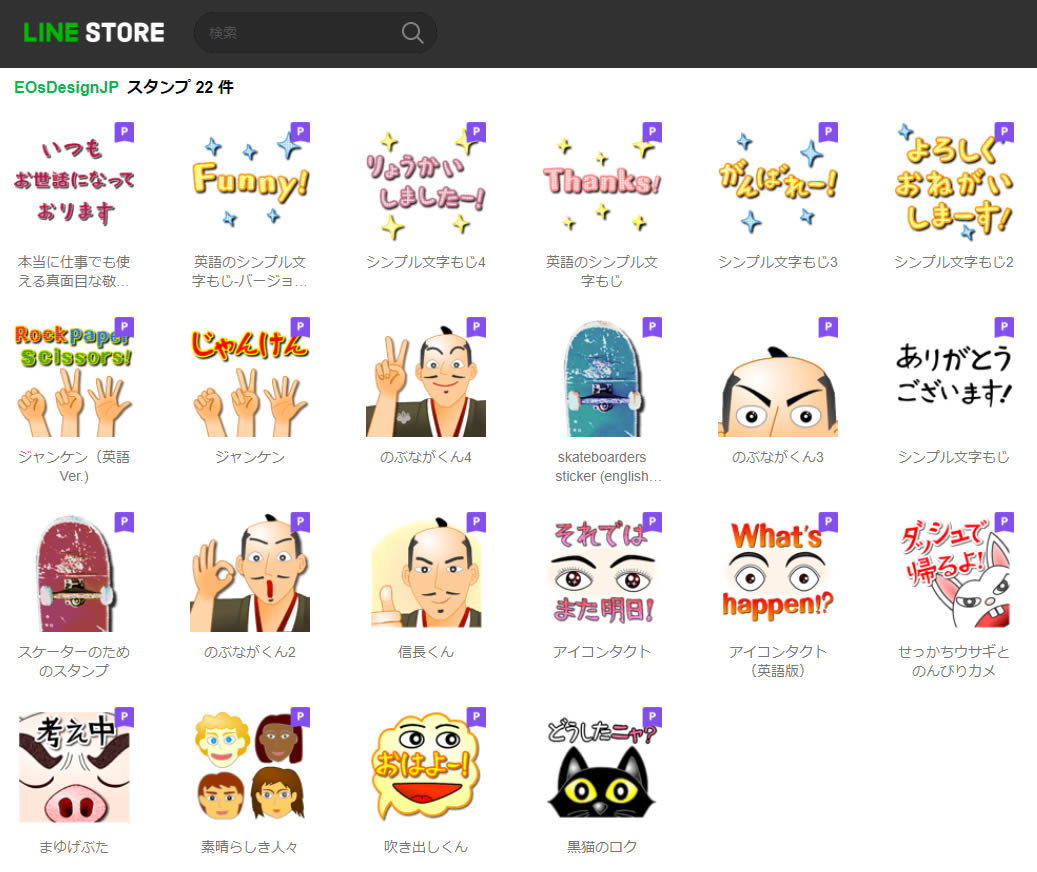「虎御前山(とらごぜやま)」は、織田信長と浅井長政との戦いの中で重要な舞台となった場所です。小谷城のすぐ南側に位置する独立丘陵で、信長が小谷城を攻める際の拠点にしたことで知られています。以下に歴史的背景と戦闘の経過を詳しくまとめますね。
⚔️背景
-
元亀元年(1570年)
織田信長と浅井長政は当初同盟関係でしたが、長政が義兄の信長を裏切り、浅井・朝倉連合軍に加担します。信長は金ヶ崎の退き口で撤退に追い込まれ、両者の対立は決定的となります。 -
元亀3年(1572年)~天正元年(1573年)
信長は各地の敵対勢力(比叡山、武田信玄、浅井・朝倉)に苦しみますが、武田信玄の病死・比叡山の焼き討ちなどにより、次第に包囲網を崩していきます。
浅井・朝倉を討つための拠点として、戦闘の最終局面の砦として選ばれたのが虎御前山です。
⚔️虎御前山砦の築城
-
天正元年(1573年)5月
信長は小谷城を攻めるにあたり、虎御前山の頂に本陣を置き、周囲に大小30以上の付け城・砦を短期間で築かせました。 -
この布陣により、小谷城はほぼ完全に包囲され、兵糧の補給も絶たれることになります。
-
虎御前山は小谷城を真正面から監視できる位置にあり、信長の戦略的優位を確立しました。
⚔️戦闘の経過
-
朝倉軍の救援戦(天正元年7月頃)
-
浅井長政の盟友・朝倉義景が援軍を出しますが、信長は虎御前山の砦群を利用してこれを撃退。
-
この時、織田軍は砦を活かして持久戦を展開し、浅井・朝倉連合軍は小谷城へ十分な兵糧を送れませんでした。
-
-
包囲戦の激化
-
織田軍は虎御前山を拠点に周辺の浅井方支城を攻略。横山城を押さえて兵站を固め、浅井軍を孤立化。
-
小谷城内では兵糧が欠乏し、士気も低下していきます。
-
-
朝倉義景の撤退
-
織田軍の圧迫に加え、義景自身の領国が混乱し、越前へ撤退。浅井軍は完全に孤立。
-
-
小谷城の最期(天正元年8月~9月)
-
信長は虎御前山から総攻撃を命じ、小谷城の支城「大嶽砦」や「中丸」を攻略。
-
最終的に浅井長政は小谷城に追い詰められ、自害。浅井氏は滅亡しました。
-
⚔️戦術的意義
-
虎御前山に大規模な砦群を築いたことにより、「包囲による兵糧攻め」が成功した好例とされます。
-
信長は「付け城」戦法を実戦で活用し、のちの長篠合戦や石山本願寺攻めなどの作戦にもつながっていきます。
-
浅井氏の滅亡は、信長にとって北近江の完全支配を意味し、以後の京都支配の基盤が固まりました。
⚔️まとめ
虎御前山での戦いは、派手な正面衝突というよりも、織田軍による包囲・砦戦術・持久戦が特徴的です。
ここを制したことで信長は浅井氏を滅ぼし、織田政権の安定に大きく前進しました。